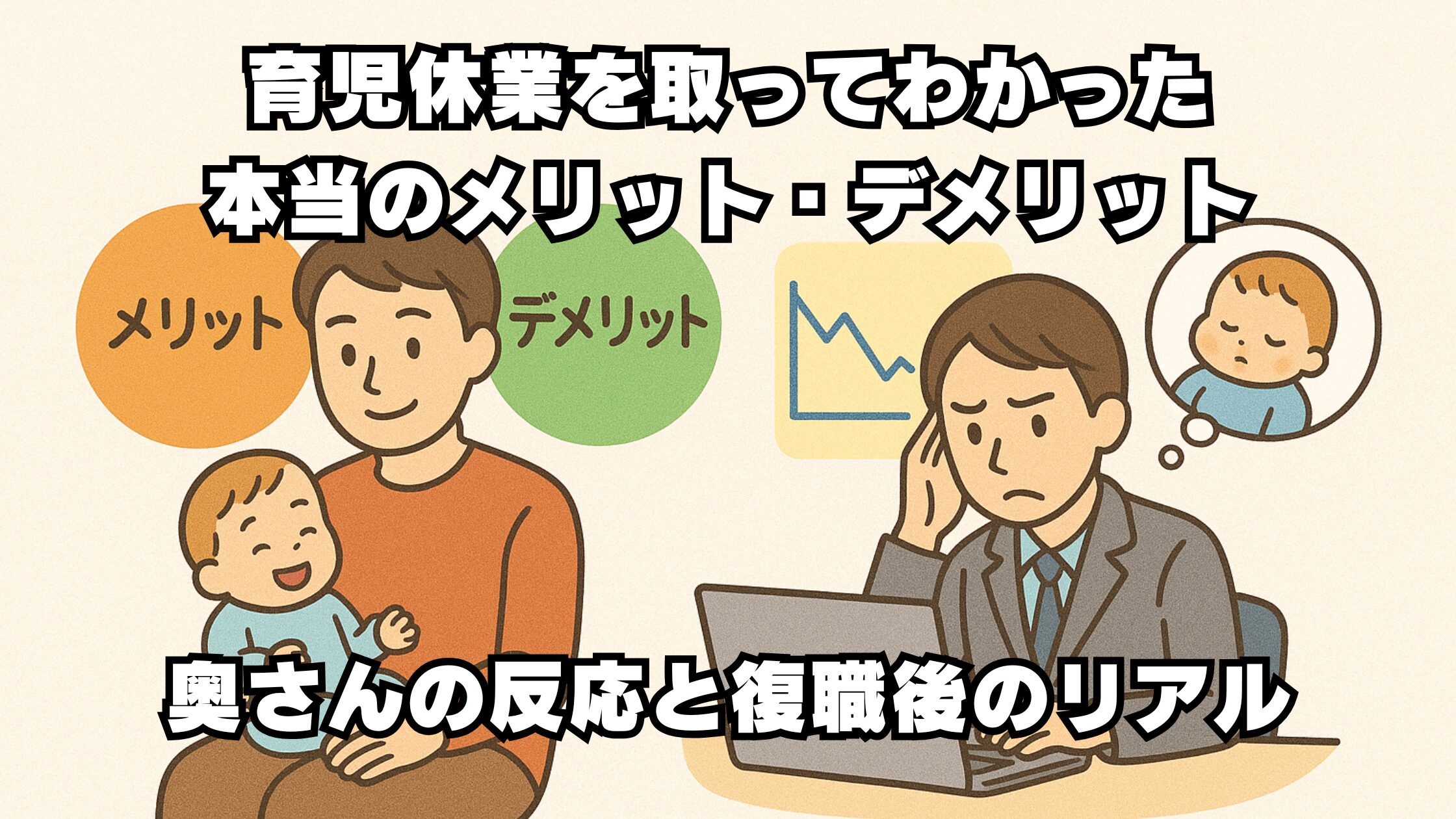私は2024年の9月頭から2025年2月末まで半年間育児休業を取得しました。

育児休業を取ってみたいけど、実際どうなんだろう?
そんな疑問を抱く方は少なくありません。
社会的には“育休推進”が叫ばれる中、現実は戸惑いと不安の連続です。
本記事では、実際に育休を取得した体験をもとに、育児休業のメリット・デメリットを包み隠さず紹介します。
また、意外と気になる奥さんの反応や、復職後の生活の変化についても深掘り。
これから育休を考えるあなたが、納得したうえで一歩踏み出せるよう、リアルな視点でお届けします。
育児休業のメリット・デメリットとは?
育休で得られる最大のメリット
- 子どもとのかけがえのない時間
これから先の人生を考えても子どもとずっと居られるのは期間はほとんどありません。
専業主婦(夫)でなければ平日休日関係なくずっと居られるのは育児休業を取った人だけの特権です。
最初は笑顔を振りまいてもなかなか反応してくれませんが2,3ヶ月ほど経てばニッコリしてくれます!
- パートナーとの信頼関係が深まる
赤ちゃんとの生活は不安の連続です。
困ったときに一緒に考えてくれる人がすぐそばにいる安心感はとてつもなく大きいです。
必ずしも正解を導き出せるかは分かりませんがこの大変な時期を二人三脚で乗り越えていけたことは夫婦関係において大きな財産になること間違いなしです。
私が心がけていたことは妻だけに大きな負担がかからないようにすることでした。
一番簡単なことで行くと例えば奥さんがあやしている間にミルクをつくること。
なにか自分にできることはないかと考えて
常に「自分も一緒に育児やってるよ!」と認識してもらうことが大事です!
• 育児スキルが身につき、長期的にプラスに働く
奥さんは病院で助産師さんに教えてもらいながら沐浴やおむつ替えを実践しているので最初は少し出遅れている感はあると思います。
ただこれもどれだけ実践するか経験するかで大きく変わります。
失敗して当たり前という気持ちで積極的に取り組みましょう。
人形を使った沐浴の方法やおむつ替えの練習などが出来るので病院やお住いの役所が開催している両親学級に参加することをおすすめします。
私も退院後すぐ実際にベビーの沐浴をしましたがこの経験が活きたと思います。
あとは赤ちゃんをあやす抱っこも積極的にやりましょう!
小さい頃から私がやったので5,6ヶ月ごろに始まった夜泣きも妻より私のほうがやるほうが早く落ち着くことも多いです。

なんせすぐ大きくなって重くなりますので男性の力は必須です!
昔は5kgのお米が重く感じましたが日々の抱っこの成果もあり、今では軽く感じます笑
・義母からの評判があがる
自分たちの親の世代では父親が仕事を休んで育児をするような時代ではありませんでした。
私も給付金が出る今の時代だからこそ育児休業を取りましたがお金がないとやはり人間生きていけません。
育児の負担が大きかった義母からは今の子たちは育児に参加して偉いと褒められます。
逆に今の時代に奥さんがワンオペだと非難をあびるかもしれませんね
思わぬデメリットもある
- 収入減による生活の見直し
給付金が出るとはいえ2024年当時は前年度年収の67%程度になってしまいます。
赤ちゃんが生まれる前にまずは固定費の見直しを行うことをおすすめします。
なかなか重い腰をあげるタイミングがないと思うのでせっかくの機会に見直してみましょう。
私がやったことといえば
収入が減ることは早い段階で分かっていることなので育児休業を取るまでの間に固定費を見直すか、収入減に耐えられるように貯金をすることが挙げられると思います。
- 社内でのキャリアや評価への影響
育児休業を取っている期間はあなたのキャリア(就労期間)には含まれません。
私の場合は6ヶ月取ったので残り半分の成果に対して正当に評価してもらえればいいのですが日本の企業で勤めていれば昇給や昇格はほぼ無いと思ったほうがいいかもしれません。
・昼ご飯を2人分用意しないといけないというちょっとしたプレッシャー
一人であれば適当にカップラーメンや納豆ご飯などで簡単に済ませられますが二人いるので何かしら用意しないといけないというプレッシャーはあるかもしれません。
当時住んでいたマンションからは自転車で5分圏内にファストフード店が多く、基本的に私が2人分を買いに行くことが多かったです。
昼ご飯まで作るのは大きな負担になるので赤ちゃんのお世話を優先して大人は極力手をかけないことをベースにすることをオススメします!
・自分はここまでやっているのに相手はやってくれないというストレス
産後すぐは奥さんの体に大きなダメージがあるので積極的にパパが動いて欲しいですが、数ヶ月経つと自分の方が頑張ってて奥さんの方があまりやってくれない時が出てきます。
例えば夜の寝かしつけです。
生後2,3ヶ月の頃はまだリズムが出来ていないこともあり30分から1時間かけて寝かしつけてました。
前日、奥さんはドラマやYouTubeをスマホで見てる横で自分が寝かしつけをしてたとします。
次の日は奥さんにやって欲しいのですが母乳の匂いもあるのか中々寝てくれず自分がやるのが当たり前のようになり自分ばっかりと不満が溜まった時期もありました。
・義両親からの手助けがない
私が育休を取ってなければ親が手伝いに来てくれたかもしれませんが2人で育休を取っているので関西圏にいる義両親は自宅に来てサポートなどはほとんどありませんでした。(取ってなくても変わらなかったか分かりませんが)
私の実家は九州にあるため私の両親は日常的に手伝いに来ることはできませんでした。
奥さんの反応はどうだった?
「 一緒に育てたい」という思いがかなった
- 「2人で育てる」という意識
当たり前に聞こえるかもしれませんが生まれてきた我が子は2人の子どもです。
しかし、日本の昔ながらの風潮からか奥さんに負担が片寄る傾向にあると思います。
私がそもそも子育てに携わりたいという思いがあったからかもしれませんが我が子と一緒にいられる時間は短いです。このかけがえのない時間を2人で協力して乗り越えましょう!
・2人がかりで子育てできるので可愛がる余裕が出来た。
一人で育児をしていたらなかなか心の余裕が無いですが、2人いることでお互いをフォローできるのでしっかり可愛がることが出来ました。
今は保育園に通わせていますが笑顔を振りまいて園の先生たちからもすごい可愛がられています
・毎日昼寝が出来た。
言わずもがなですが睡眠不足に陥ります。私たち夫婦は元々2人ともしっかり8時間は寝るタイプでした。
生まれて間もない頃は3時間おきにミルクをあげるので夜中に起きるのがとても大変でした。
1人で赤ちゃんのお世話が出来れば片方が起きて赤ちゃんを見ておけばもう片方は寝る時間が確保できるので育休中は日中にお互い1時間は昼寝の時間を設けていました。
今振り返れば育休復帰後の夜泣きが酷かった時期に比べれば育休中の睡眠不足は大したことなかった気がします。
パートナーシップの再構築に繋がる
• 価値観のズレに気づき、より良い関係へ
もとは別の家庭で育っているわけなので多少なりとも価値観が異なるのは当たり前だと思います。
例えば赤ちゃんがおむつを替えてすぐにうんちをしたとしましょう。
私は極力自分の手を割きたくないのである程度時間が経ってから替えたいですが妻は極力赤ちゃんが快適であるようにしたい
例えば赤ちゃんが夜、別の部屋で寝ていたとしましょう。
私は極力音を立てないように扉はゆっくり閉めるし、音で起こさないように配慮しますが妻はある程度の音を立ててもどうせ起きないと思って普段通り。
といった感じです。こんな些細なことでも考え方は異なります。
育児に関係なく「何を大切にすべきか」を夫婦でよく話し合って摺合せをしましょう。
「言わなくてもわかるだろう」と過信しないほうがいいかもしれません。
- 家事や育児の負担が分散されて感謝の言葉が増えた
「ありがとう」と言われて不快な人はいないと思います。
何も言わないよりかはもちろんいいですがただ育児や家事をどちらかが負担しているのでは意味がありません。あくまで分担することでお互いの大変さが分かったうえでの「ありがとう」が響くのではないかと思います。
復職後の生活はどう変わった?
働き方への意識が変化
- 時間の使い方がシビアに
保育園の送り迎えがあるので朝の園の送りは妻にお願いし、お迎えは私が行くことになりました。
会社がフレックスタイム制を導入しているので標準の業務開始時間より1.5時間早めの7:30に出社し、その分前に退社するようにしました。
私たちは標準時間認定のため18時までに迎えに行けばいいのですが通勤時間もさほど多くかからないため17時ごろには保育園に迎えに行くようにしました。
妻の会社はフレックスタイム制を導入していないため1時間時短勤務で復職しましたがそれでも大変だったので8月から2時間時短勤務にしました。
私の業務は縦割りなので自由が効くのですが妻の場合は誰かと一緒にやっていることが多いので業務内容の共有や引き継ぎは重要なポイントのようです。
・睡眠の質をあげる。
業務時間が短くなるのでその短時間で成果を出すには睡眠の質をあげて高パフォーマンスで仕事をする必要があります。
我が家では日替わりで子どもの夜泣き対応を行うことにし、担当じゃない日はしっかり寝ることに注力しました。
とはいえ夜泣きが1時間以上続いている場合などはサポートするなど臨機応変に対応しました。
職場の反応と自分の変化
- 周囲の見る目が変わった?
ここは正直分かりません。
少子化である日本において子育て世代を職場全体でフォローすることが望ましいです。
私の場合は夜泣きがひどいことや妻の体調不良など包み隠さず話すことでなにかあったら助けてほしいということは職場では話していました。
とはいえ業務量が減ったようには感じないので睡眠不足の中奮闘しています!
- 昇進や評価への影響は本当にあったのか?
育児休業を取る=勤続年数に含まれないので正当な評価はされないように感じます。
私の場合はほぼ下期の半年間で育児休業を取りました。
上期の業務成績でいえばそれなりに評価されてもいいと思いますが期末評価はB(普通)でした。
会社の社風にもよると思いますがまだまだ正当な評価はされにくいのが事実です。
• 自分の働き方を見直すきっかけになった
育休中の2024年度と復帰後の2025年度で上司が変わり(元々同じ部署で働いていた人がスライドで昇進)今後の自分のキャリアパスについてなんとなく話がありました。
その中で上司から言われたのは「クッパパさんは〇〇さんよりまだ若いから3年から5年くらいかけて昇給になるかも」ということです。
私の会社ではまだまだ年齢で判断されることが多く、担当している業務を考えるともう少し昇給してもいいはずが数年変わらない可能性が高いと言われました。
これは育児休業を取ったことによるものかどうかは不明ですがこれから子どもを育てるにあたりお金は必要なので転職も1つ視野に入れておこうと思いました。
ひとまず「ビズリーチ」と「リクルートダイレクトスカウト」の2つに登録し、まずは自分の市場価値を確認しているところです。
転職が当たり前になってきている時代ですので給与に不満があれば一度自分の市場価値を高めるためにも転職サイト(エージェント)を使うのもいいと思います。
Q&Aセクション
Q1: 育児休業ってどれくらいの期間取るのが理想?
A: 家庭の状況によりますが、最低でも3ヶ月は育児や家事に集中できると、実感も変わります。
産後の体は交通事故にあったようなダメージといいます。最初の1ヶ月は慣れる期間と思っておくと◎。
私の妻曰く「最初の1ヶ月なんてずっと横になっているだけ。大変なのは動き出してから」と3ヶ月は取ってほしいと言っています。
お金の心配もありますが3ヶ月は取ってほしいです。
Q2: 奥さんは育休に入ることを喜んでくれる?
A: 最初は分からないことだらけです。一緒に悩んだり相談できる相手がいることは安心につながるので絶対喜んでくれます。育休前に最低限の家事はできるようになっていればよりいいです。
Q3: 職場復帰後の評価は落ちませんか?
A: 一部では偏見があるのも事実。しかし、復帰後のパフォーマンスで十分取り返せますし、時代の変化も追い風になっています。
評価されにくいという現実はまだまだあるかもしれませんが腹を括りましょう。
Q4: 育休中にしておいてよかったことは?
A: 育休中は育児に専念してほしいですが、少し慣れてきたら近場に旅行に行ってもいいと思います。
平日に行けるので人も少なく安く行けますしリフレッシュにもなります。あとは実家への帰省です。飛行機を使う場合などは移動だけでかなり疲弊するのでどこかで経験しておくほうがいいです。
Q5: 男性が育休を取ることに不安があります。何から始めれば?
A: まずは奥さんとオープンに話すこと。給付金があるとはいえ収入減になるのでよく相談しておきましょう。次に上司への相談と情報収集を。
独身時代からでも育休を取りたいことを同僚に話しておく(根回ししておく)ことが重要です。
あとは身近に育休を取った人がいるのであれば経験談を聞いておくといいでしょう。私に問い合わせていただいてもかまいません。
男性の育休取得も増えてきています。労働者の権利なのでちゃんと包み隠さず話をしましょう。
まとめ
育児休業には数多くのメリットがある一方で、想像以上にリアルなデメリットも存在します。
ですが、それらを知っておくことで備えることができます。
奥さんの反応も、最初は不安でも、やがて感謝へと変わるはず。
そして復職後の生活もまた、育休前とは違う“新しい視点”で充実したものになるでしょう。
自分自身、家族、そして仕事。そのすべてを見つめ直す絶好の機会として、育児休業は今、人生を豊かにする選択肢のひとつです。
「仕事の代わりはいるけど親の代わりはいない」という言葉は育休を取って改めてその通りだと思いました。
育休を取って一番良かったと感じるのは子どもがいろんな人にニコニコして、愛想がよく可愛がられることです。
一人で面倒を見るのはとても大変です。夫婦で力を合わせて乗り越えましょう!
以上、クッパパでした〜